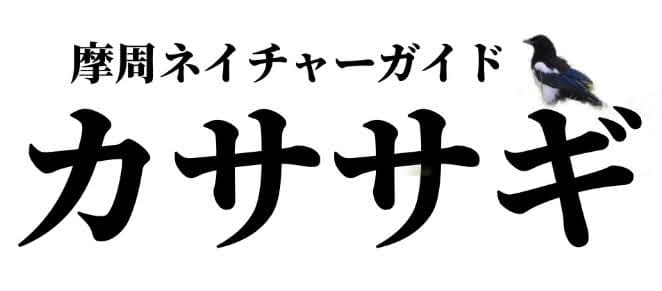前記事の続き…ドドッと写真
前記事では紹介しきれなかった写真をドドッとお届けします。どうぞ~!

可愛らしく野に咲くイチゴのお花。エゾノクサイチゴは自生種ですが、姿がよく似たエゾヘビイチゴ(俗にいうワイルドストロベリー)は帰化植物です。もともとはヨーロッパで生活をしていましたが、明治ころから日本へ来て繁殖しています。北海道でも公園や道端でよく見かけます。世界各地で生息域を増やしているようです。”エゾ”ヘビイチゴとありますが、北海道の固有種ではなく、”北海道”に咲くヘビイチゴ(正確にはヘビイチゴではない)となります。パッと見の違いとしては、おしべとめしべの長さの違いでしょうか。エゾノクサイチゴは写真のように雄蕊(おしべ)が雌蕊(めしべ)より長い。エゾノヘビイチゴは雄蕊と雌蕊が同じ長さなのが特徴です。もし見かけた際は、観察してみてください。

足元をよ~く見ていないと気づかないほど、小さくポツンと咲くフデリンドウ。小さな体でもこんなに美しい紫色を輝かせるその姿に感銘を受けます。今年も出会うことができました。

ミヤマ=深山。山奥に咲くスミレ。葉っぱ表面の葉脈に沿って白い斑が入るものを”フイリミヤマスミレ”と言います。

和琴半島でも咲いていたコヨウラクツツジ。標高の高いこの場所でも咲いていました。ピントがブレブレですいません…。

こちらは白いスミレ”ツボスミレ”です。とっても小さい体なので慣れないと見過ごしてしまうかもしれません。そんな小さなスミレですが紫色のガイドラインがあることで、虫たちが「ここに蜜があるぞ~」と立ち寄ってもらえるようになっています。小さな体でも、賢く生きています。写真がブレブレでスイマセン…汗

名前の通り、大きなタチツボスミレです。花柄が茎の途中から出るので、パッと見で他のスミレとの違いに気づきやすいかと思います。

和琴半島では咲いていたズダヤクシュ。こちらではこれから先始めるようですね。ズダヤクシュは漢字で「喘息薬種」と書き、長野県では”ズダ”が喘息を意味していて、この植物が喘息に聞くことで名づけられたそう。

展望台よりも近くで見る摩周岳。近くで見るとより威厳さをビシビシ感じますね。この日は頂上まで行きませんでしたが、この距離でも堪能できるのが凄いですね。

ミヤマカラスアゲハがスミレの蜜を吸っていました。一つ一つ一生懸命に吸っている様子がなんとも可愛らしかった。「頑張れー!」と心で応援しちゃいました…(笑)
こんな場所にミヤマカラスアゲハが生活しているのですね。以前、千歳市の支笏湖周辺の山、風不死岳を同じ季節に歩いたときにも、ミヤマカラスアゲハが飛んでいて「こんなところで生活しているんだなぁ~」と感心した思い出があります。まさか故郷でも同じく生活しているミヤマカラスアゲハがいるとは…感動だなぁ。

ここからの景色が好きです。稜線が伸びて…西別の山が見えて…高い建物が無い牧草地、農地…その上には青い空と白い雲。
大自然が広がる世界にちっぽけな存在の私。人は地球の一部なんだと感じさせてくれる場所。自然を大切にしようと心湧かせてくれる場所。
さて、今回は摩周に咲くお花たちと風景をお届けしました。皆様もお立ち寄りの際は、絶景の摩周湖を楽しみつつ、足元の可愛らしいお花たちを観察してみてくださいね♪