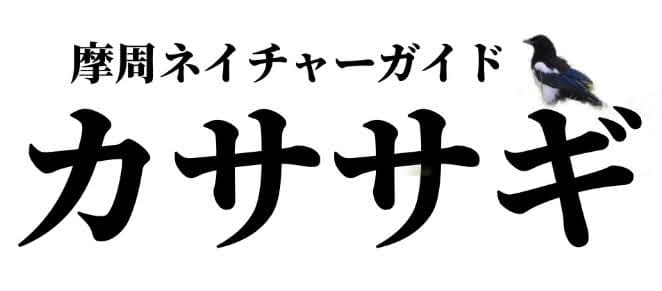ムシトリナデシコ
皆様はこのようなお花を見かけたことはありますか?
ピンク色の綺麗なお花をつけるこの植物です。よく道端に咲いているので、見たことがある人は多いのではないでしょうか。
この植物はムシトリナデシコというお花です。大体は膝下くらいの背丈で、大きいものはそれより高くなるそうですね。

さて、そんな綺麗な植物の名前に”ムシトリ”という文字が入っていますね?
漢字にすると”虫取り”で、文字通り虫を取ることが由来になっています。
茎に1㎝程度の範囲でベタベタする粘性の茶色い部分があるのですが、この部分に虫がくっつき、じたばたとしている様子がまさしく虫取りとなるわけです。
虫を捕るということは…食虫植物なのか?というとそうではありません。虫を食べるために取るのではなく、虫を登らせない(蜜を守る)ために取るということ。ハチやハエは蜜を求めて花に来て、その時に体に花粉をいっぱい着けていき、他の花に移動し、受粉をする…という相互関係・お互いがお互いのためになる関係となりますが、アリはそうではありません。
アリは花を食べてしまったり、蜜を取っていく(盗む)だけで、花粉を運んでくれない…というあまり嬉しくない存在なのです。
そんなアリから守るためにベタベタの分泌を出し罠を設置することで身を守っているわけですね。
ここまでムシトリナデシコの賢い生存戦略のお話をしてきました。もう気づいている方がいるかもしれませんが、写真では茶色いベタベタの部分が写っていないんです。そう全部が全部このベタベタがあるわけではないんですよ!そこが面白いところですよね。
なんでベタベタが”有る個体”と”無い個体”があるのか。その違いはどのような理由があるのか。
これを知るには一つ一つの個体をよく観察し、成長段階や生息環境などを考慮し、多くのデータを元に導く事が必要です。
ですがこのような研究心を持ってムシトリナデシコを見る人はいないでしょう。
この研究をして新しい発見があれば、もしかしたら有名人になれるかもしれませんよ(笑)
さて、ここからはおまけのお話をしたいと思います。
ムシトリナデシコは水と一緒にゴシゴシこすると泡立つ…という面白い作りになっているそうです。
昔おばあちゃん家でやったわ~なんて経験ありますか?
ちょっと気になったので実際にやってみました!

水を溜めて、ムシトリナデシコを投入。
もみもみ。ゴシゴシ。ギュっギュッ。
気になる結果は…?

泡立ちませんでした!(笑)
やり方が違ったのかな?今度またリベンジしたいと思います。