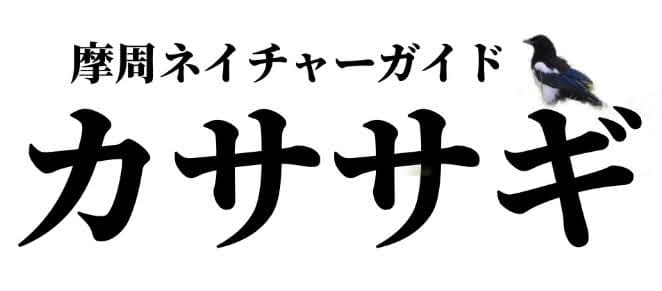クロユリの面白い生態

和琴半島にクロユリが咲いていました。クロユリは北海道全体的に分布しているわけではなく、十勝・帯広・小清水など、ある程度の範囲に限られています。その中で和琴半島にも咲いている…というのは貴重な事なのだと思います。
さてこのクロユリですが、なかなか面白い生態をしています。
まずはお花の香りです。良い香り!ではなく”悪臭”を放っているお花なのです。英語では「skunk lily]というくらいですから。
人にとっては悪臭なのですが、このにおいが好みの虫がいて花粉を運んでもらう戦略を取っています。
花粉を虫に運んでもらうわけですが、お花の作りが2パターンあります。1つは雄しべだけを持つ雄花、もう1つは雄しべと雌しべ両方を持つ両性花です。茎の先に2~3個の花を付けますが、毎年同じ花をつけるわけではないんです。(今年雄花が咲いていて、来年も同じ雄花が咲く、ではないということ)
どうやら地下にある鱗茎の大きさによって変化するようで、初めのうちはある程度大きくなるまでは葉っぱが1枚だけの状態で成長し、次に茎を伸ばすだけ、さらに鱗茎が大きくなると雄花が咲き、次いで両性花を付けます。そして2つ3つと付けていくようになっていき、雄花と雄花、雄花と両性花、両性花と両性花など様々なパターンで花付けます。クロユリが花をつけるまでに何年もかけてちょっとずつ成長していく植物なんです。
実を結び種子ができて繁殖する…のですが、その種子の発芽率がよくなく、クロユリの繁殖のほとんどが鱗茎が分裂して増えていく栄養繁殖と呼ばれる繁殖の方法となります。つまり、遺伝子が同じクローンを増やして種を残してきたということ。
実に面白い生態だと思いませんか?

さぁお花を近くで観察してみましょう!

黄色いマンゴーアイスバーみたいなのが雄しべ(の葯と呼ばれるもの)で、ニョキっと3つに分かれた緑のやつが雌しべです。写真のクロユリは雄しべと雌しべがあるので両性花であり、2つあるということ。鱗茎は随分成長していると思われます。
さて、ではここに咲いているクロユリはどのようなパターンで花をつけているのか?気になりませんか?
ということで全てのクロユリを観察しパターンはどうなっているのか確認してみました。
結果は…
全て両性花でした。約30個すべてです。
2024年和琴半島の約30個のクロユリは両性花でしたが、来年はどうなるのか?雄花が増えるのか、変わらないのか、楽しみですね~♪
なんてちょっとマニアックな遊びをして楽しんでいました(笑)
皆様もクロユリを見つけた時は、そんな視点でみて楽しんでみてくださいね!植物の知の沼に一緒に入りましょう(笑)